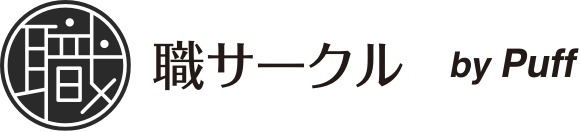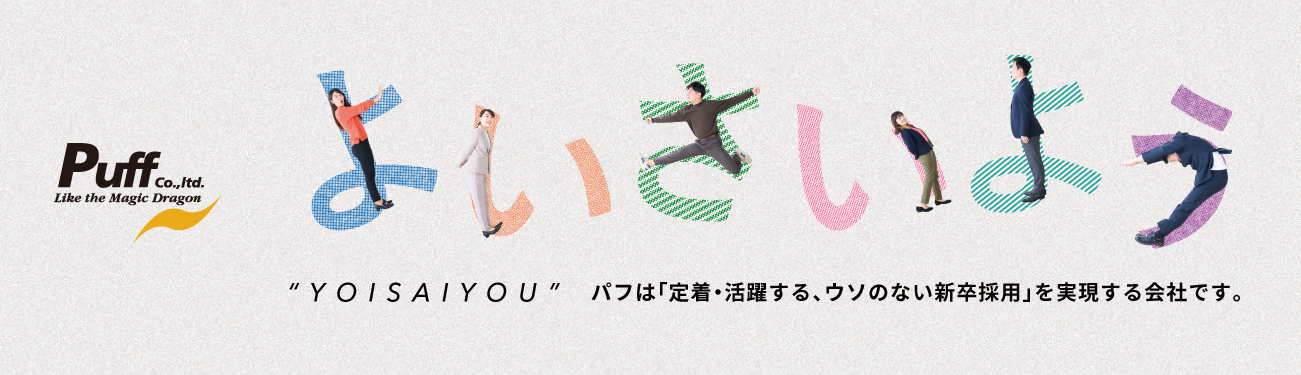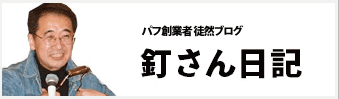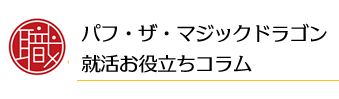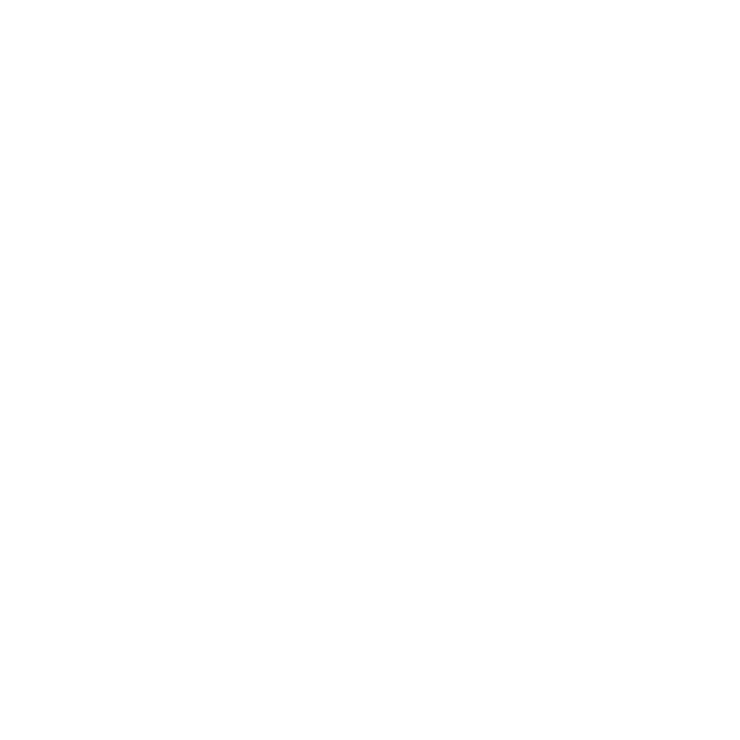
人事インタビュー
「選ばれる」だけじゃなく「見極める」就活を ― 自分に合う会社の見つけ方
株式会社ヨコソー
川部 高志・軍司 彩里(経営企画部 人事課)
企業に「選ばれる」だけじゃない。自分自身で「いい会社」を見極めよう!
自分にとっての「いい会社」ってなんだろう?
改めて聞かれると、意外と難しいな、と思う方が多いのではないでしょうか。
「一緒に働く人たちがどんな人たちなのか。居心地良く働けるか。私にとってはそこがすごく大事でした」とご自身の就活を振り返るのは、株式会社ヨコソーの人事担当者・軍司さん。
そんな「人との相性」が決め手だったという軍司さんは、選考中にヨコソーの社員数名と面談をする機会をもらったこと、そのときの対応がとても印象に残っているそうです。
「当時の就活での悩みに、すごく親身に寄り添っていただいたんです。『絶対うちがいいよ』なんて売り込むことは全然なくて、『それなら他の会社を選んだほうがいいかもね』って、あくまで私の立場で一緒に考えてくれるような雰囲気でした」
都合を押し付けることなく、まず話を受け止め、自分を認めてくれる姿勢が、「こんな会社で働きたい」と思った理由のひとつだといいます。
軍司さんが大事にしていた「居心地の良さ」は、数値やデータでは測れないもの。でも、だからこそ大切な視点ともいえます。ヨコソーという会社がもっている「安心感」は、いったいどこからくるのでしょうか。
例えば、ヨコソーは、成果をすぐに求める“短距離走型”ではなく、じっくり育てる“マラソン型”のスタンスで社員教育を行っています。新入社員は1年間かけて研修を受け、いきなり現場に放り込まれることはありません。育成に時間をかけ、焦らず力を伸ばす体制が整っています。
「最初から成果を求められるのは不安だったので、このスタンスが私にはすごく合っていました。中には“早く力をつけたい”という人もいると思うので、そこは合う・合わないがあると思います。でも、“ちゃんと見てくれる会社がいい”という人には、すごくフィットする会社だと思います」
この「合う・合わない」という感覚を、同じく採用担当で責任者でもある川部さんもとても大事にしています。
「学生の皆さんには、就活中、単に“見られる立場”だと感じてほしくないんです。むしろ、会社側も“学生に見られている”という意識を持っていないといけない。そんなオープンな関係性の中で、お互いに『合うかも』と感じられたら嬉しいですね」


“ご縁”を育てる仕事──修繕工事の底力と将来性
「建設業」と聞くと、多くの人が新しくビルや住宅を“つくる”仕事を思い浮かべると思います。でも、ヨコソーが手がけているのは、“なおす”仕事──「修繕工事」です。
築12〜15年ごとに実施される「大規模修繕工事」は、建物の安全性や資産価値を守るために欠かせないメンテナンス。目立たないけれど、なくてはならない、社会の基盤を支える仕事です。
そしてこの事業は、ものすごく“安定”しています。
「修繕工事は『やらない』」という選択肢が基本的にないんです。タイミングは物件によって差があるものの、劣化が進み、いつかは必ず必要になります。いわば「車検」や「健康診断」のようなもの。絶対に避けて通れない分、ビジネスとしても継続性が非常に高いのです」と川部さんはおっしゃいます。
「あったらいいな」ではなく「なくてはならない」、例えるのであれば、「建物のかかりつけ医」の様なビジネスのひとつとも言えますね。
営業活動にも事業の特性が現れています。1つの案件について、実際に工事が着工するまでには、3年程度かかることもあるとか。数年前からご相談を受け、関係性を築き、プレゼンや見積りを経て受注。そして着工後も、場合によっては年単位にわたる工事期間を経て、さらにその1年後のアフター点検、工事内容によっては10年後のアフターメンテナンスまで、お客様と長期にわたって担当者が関わるそうです。
さらに、お客様から「前回対応してくれた○○さんに、今回もお願いしたい」というお声があがり、リピートに発展する機会も少なくないのだとか。実際に前回担当した社員がすでに管理職となり現場を離れていても、新担当者と一緒にご挨拶に再訪することで安心感を与えている例もあるそうです。
「だからこそ、ヨコソーは簡単に担当を変えない方針を貫いています。もし転勤や部署異動があった場合でも、できるだけアフター点検までは“最初の担当者が責任を持つ”というのが基本。それが、信頼の積み重ねにつながっていると思います」
さらに注目すべきはビジネスモデル。
製造や販売を事業としている企業が、販売するところまででお客様との関係性が一区切りを迎える“フロー型”のビジネスを展開する中で、ヨコソーのような修繕事業は“繰り返し”が前提、かつビジネスサイクルの期間が長い“長期ストック型”です。
対象となる建物(特にマンション)は年々増加しており、首都圏だけでも膨大な数が存在します。
つまり、将来的にも修繕の需要がなくなることはまずない、ということですね。
加えて、人口減少や少子高齢化などの社会的なリスクが懸念されている中でも、「売上の計算式に人の数がはいらない」ということも大きな強みといえます。たとえ居住者数が減ったとしても、建物が存在する限り、修繕は必要になります。
このように、ビジネスの堅実性を裏付ける、「信頼重視」「繰り返し」「長期視点」という修繕事業の特徴・要素は、そのまま社風や働き方にも大きく影響しています。
たとえば、社員の定着率の高さ。現場に長く関わる必要があるため、頻繁な異動が起きにくく、社員一人ひとりが「自分の現場」に責任を持って取り組める環境が整っているといえます。
「すぐに成果を出すことよりも、丁寧な関係づくりや誠実な仕事ぶりが評価されるため、『コツコツ型』、『対話重視』の方にとっては、無理なく活躍できる職場だといえるでしょう」と川部さんはおっしゃいます。
実際、ヨコソーが業界内で高い評価を受けている背景にも、こうした「誠実な仕事ぶり」があります。
「安さを重視して品質を落とす」ことを良しとしないヨコソーは、入札において最安値を提示することは少ないそうなのですが、それでもお客様から「前回の対応がよかったからまたお願いしたい」と選ばれるケースが非常に多いのだとか。
価格ではなく、信頼で選ばれる──それこそが、ヨコソーという会社の真価であり、ビジネススタイル、そして働き方にもあらわれています。
会社の雰囲気や営業スタイルなど、ともすると「入社してみないとわからない」と諦めてしまいがちですが、実はビジネスモデルや商品のサイクル、企業の価値観がそれらを形成する大きな「原因」であるということ。
ぜひ、就活で注目していただきたいポイントです!

もう一つの顔
就職活動では、一般的に「会社説明会」「一次面接」「二次面接」…という選考フローをたどりますが・・・。
「うちの選考は“会話”から始まります。いきなり会社説明や志望動機ではなく、まずは学生の話を聞くことから。そこに、どんな人柄があるのかを見たいんです」そう語るのは、人事の川部さん。
ヨコソーでは、選考の中で「FFS診断」というツールを活用し、学生が自分の強みや価値観を客観視できるようサポート。そのうえで、学生自身のスペックではなく、「本質的な気質」や「自然な強み」にフォーカスした対話を行っています。努力して身につけたスキルよりも、その人の“素”に近い部分を見つけにいく──それは、会社のカルチャーにフィットする人材との出会いを大切にしている証です。
「強みは、努力して身につけたものじゃなく、自然にできてしまうことの中にある」この考え方のもと、面接では学生が口にする“強み”に対して、「それってこういう見方もできるよね?」とフィードバックを行うことも。学生にとっては、ただの選考ではなく、“自分を知る時間”にもなりますね。
また、ヨコソーでは「誠実さ」を大切にしています。たとえば、現場調査の結果、「今はまだ修繕のタイミングではない」と判断したら、無理に工事を勧めることはしません。目先の利益よりも、長期的な信頼関係を重視しているからです。
そしてこの「誠実さ」は、採用の場でも変わりません。
「学生に対しても嘘をつかず、飾らず、『うちに合う人と出会えたらラッキー』くらいのスタンスでいるようにしています」 と川部さんはおっしゃいます。だからこそ、学生も自然体で向き合える。
「まずは一度、会って話してみませんか?」それが、ヨコソーの“もう一つの顔”。
形式にとらわれず、“人対人”のフラットな関係を築こうと、まっすぐ向き合う姿勢が、この会社の採用の原点です。